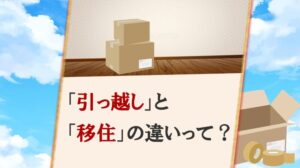Life/「未来への優しさ」が感じられる仕組みを
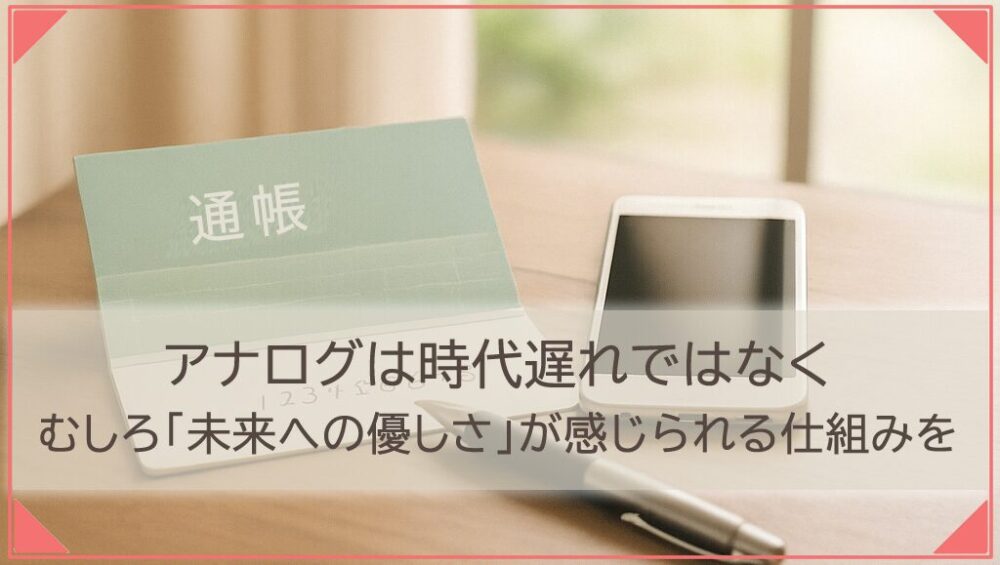
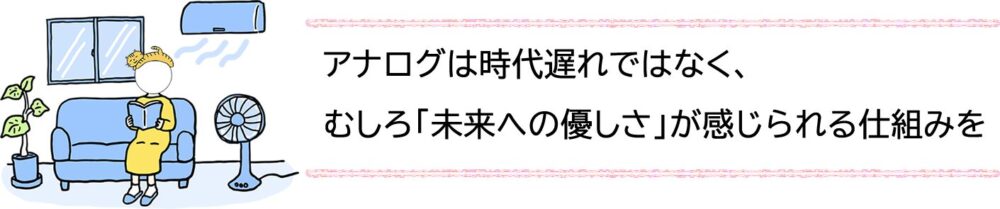
❖「デジタル前提」の流れ
近年、通帳のペーパーレス化や行政手続きのオンライン化が進み、私たちの暮らしはどんどん「デジタル前提」へと変わってきました。
便利で効率的。若い世代にとっては当たり前になりつつあるこの流れも、少し視点を変えてみると、意外な盲点があるように思います。
たとえば「紙の通帳」

すでに多くの銀行では新規発行をやめ、PCやスマホでの管理が推奨されています。
けれど、もしも本人が突然亡くなったり、認知症になったりしたとき、家族や周囲の人はどうやってその存在に気づき、どう対応すればよいのでしょうか。 若い家族がいれば、ネットバンキングの履歴をたどることもできます。
若い家族がいれば、ネットバンキングの履歴をたどることもできます。
でも、高齢者同士の家庭や、スマホに馴染みのない方が残された場合、デジタル情報は「そこにあるのに触れられない」ものになってしまうかもしれません。
いくら紙にメモを残してあっても、それがログインIDなのか、パスワードなのか、何に使うのか分からないまま、ただの「数字の羅列」として放置されてしまうこともあります。
![]() 「紙の通帳」「ウェブ上の通帳」どちらの方がよいかは、自分の好き嫌い、現在の生活環境によっても変わってくるものです。
「紙の通帳」「ウェブ上の通帳」どちらの方がよいかは、自分の好き嫌い、現在の生活環境によっても変わってくるものです。
私個人としては、現時点でのことになりますが銀行の用途別に、紙の通帳とウェブ上の通帳を使い分けています。
❖アナログは “人から人へ繋がる” ちょっと面倒な仕組みではあるが 

人生の終わりに向けての準備(いわゆる終活)の分野では、さまざまな対策やサービスが存在します。しかし多くは、アナログの手順が引き継がれ、手間・費用・労力を伴い、決して簡単とは言えません。
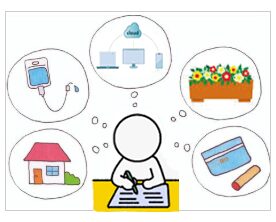
![]() たとえば一部の銀行が提供する「予約型代理人サービス」は、医師の診断書とともに、代理人を伴って実際に出向いて複数の書類を作って、となります。
たとえば一部の銀行が提供する「予約型代理人サービス」は、医師の診断書とともに、代理人を伴って実際に出向いて複数の書類を作って、となります。![]() また、「自分の財産を誰かの役に立てたい」と考えても、寄付の手続きがあまりに複雑であれば、実行に移すこと自体が大きな負担になります。
また、「自分の財産を誰かの役に立てたい」と考えても、寄付の手続きがあまりに複雑であれば、実行に移すこと自体が大きな負担になります。
 1例として、救急車購入に役立ててほしいという寄付も、「はい、どうぞ」では済まず、複数の箇所を経由、手続きを踏んで・・手間暇かけての書類を伴わなければできません。
1例として、救急車購入に役立ててほしいという寄付も、「はい、どうぞ」では済まず、複数の箇所を経由、手続きを踏んで・・手間暇かけての書類を伴わなければできません。
![]() 以前、ニュースで、正体不明の寄付金が役所にそっと置かれていたという話がありました。きっとその背景には、「名前を出して手続きを踏むよりも、静かに役立ててほしい」という優しさと、制度の壁へのあきらめがあったのかもしれません。
以前、ニュースで、正体不明の寄付金が役所にそっと置かれていたという話がありました。きっとその背景には、「名前を出して手続きを踏むよりも、静かに役立ててほしい」という優しさと、制度の壁へのあきらめがあったのかもしれません。
もちろん、デジタル化は便利さと効率をもたらし、多くの場面で私たちを助けてくれます。ただその一方で、最後に誰かへ託したい想い、未来に残したい優しさが、デジタルの壁によって遮られてしまうことがないように。
「アナログは時代遅れ」――そう思われがちな今だからこそ、
♥紙に書くこと
♥手渡すこと
♥目に見える形で残すこと
の大切さがもう一度見直されてもいいように感じることがあります。
それは決して時代に逆行することではなく、むしろ「人にやさしい未来」へつながる第一歩なのかもしれないと思うのです。